心臓のポンプ機能を機械的に代行させる医療機器「人工心臓」とは?
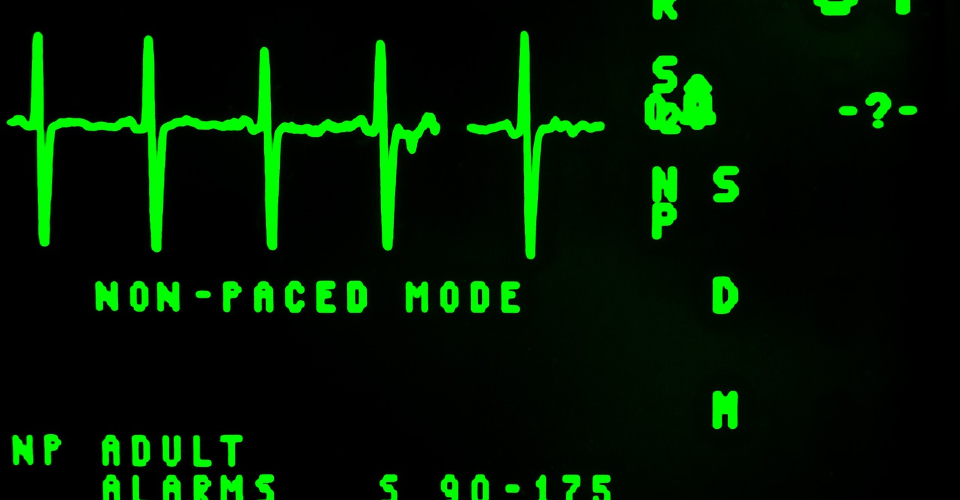
「人工心臓」とは、本来の心臓が行う血液循環を司るポンプの役割を機械的に代行させる医療機器です。
そこで、人工心臓を使用する目的や、その特徴やどのように技術が進歩しているかについて解説していきます。
人工心臓を使用する目的
人工心臓を使用する目的は、主に次の2つです。
・半永久的な使用で血液循環を維持する
・心臓移植のドナーが見つかるまで一時的に血液循環を維持する
もともと人工心臓は永久的に使用することを目的とされていましたが、脳血栓症をきたすといったリスクもあります。
末期重症心不全の治療法である心臓移植を行えば、そのリスクは軽減されると考えられるものの、ドナー不足などですぐに移植できない状態です。
そこで、半永久的な使用ではなく、ドナーが現れるまでの一時的なつなぎとして、人工心臓をブリッジ使用されるケースもあります。
1990年頃からはブリッジ使用を目的とした左心補助心臓が主流となり、その当初は人工心臓本体が体内に植え込まれて体外ではコントローラーやバッテリーなどがケーブルで連結されている状態でした。
しかし技術は進歩し、対外の大きな機械はウエストポーチサイズまで小さくなり、バッテリー交換で外出することもできるようになっています。
今後は体内にコントローラーが植え込まれるようになり、バッテリーも体外で充電して使えるようになるようです。
人工心臓の進化
人工心臓はブリッジ使用を目的とした、限られた期間のみの使用で利用されることも増えています。
それにより患者の生活の質も向上させるようになりましたが、1990代末頃からは永久使用を目的とする左心補助心臓の臨床応用も始っています。
本体は次世代の血液ポンプも開発され、従来までの拍動型血液ポンプであれば植え込みできる体格に制限がされていたものの、次世代タイプはロータリーポンプで小型化が可能とっていることがメリットです。
羽根車が回転することで血液が送り出される仕組みとなっており、遠心ポンプと軸流ポンプの2種類があります。
欧米よりも体格が小柄な日本人でも植え込むことができる大きさで、2000年からは軸流ポンプの臨床治験がヨーロッパなどでスタートしていることから、今後は期待が高まるといえるでしょう。
重症末期心不全の治療方法に人工心臓が活用されるようになり、日本発の人工心臓がいずれ実用化されるようになる日も近いと考えられます。













