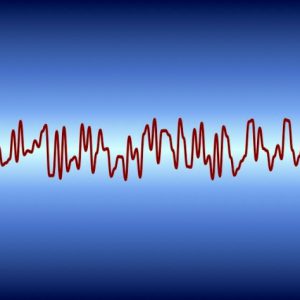ワクチンとは?仕組みや種類・それぞれの特徴をわかりやすく解説

ワクチンとは、感染症の原因である病原体に対し、免疫をつけたり強化したりする予防接種といわれる方法です。
感染症にかからないようにするために、前もって病原体に対する抵抗力を免疫としてつけるための予防接種といえます。
そこで、ワクチンについて、仕組みや種類、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
ワクチンとは
ワクチンとは、毒性ともいえる病原性をなくしたり弱めたりした病原体の一部などを、体内に接種して病原体の侵入に備える製剤です。
重篤な感染症を予防するために、病原体が侵入しても免疫システムが速やかに病原体を攻撃・排除できるようにします。
ワクチンを接種する予防接種では、感染症の原因であるウイルスや細菌などの作り出す毒素の力を弱めた予防接種液を体へ取り入れることで抵抗力(免疫)をつくります。
ワクチンの種類
ワクチンの種類は、以下のとおりです。
・生ワクチン
・不活化ワクチン
・トキソイド
それぞれ説明します。
生ワクチン
生ワクチンは、生きたウイルスや細菌の病原性(毒性)を抑えて、免疫を作ることのできるギリギリの状態で弱めた製剤です。
免疫は自然感染したときと同じ流れでつくられるため、一度接種しただけでも免疫を作ることができます。
ただし免疫力は自然感染したときよりも弱くなるため、5~10年後に追加で接種を受けたほうがよい場合もあります。
ロタウイルス感染症・結核・麻しん(はしか)・風しん・おたふくかぜ・水痘・黄熱病 などの疾患を予防する目的で生ワクチンが使われます。
不活化ワクチン
不活化ワクチンとは、ウイルスや細菌の病原性(毒性)を排除し、免疫を作るために必要な成分のみで作った製剤です。
毒性は完全にないため、接種しても対象の疾患にかかることはありません。
ただし1度接種しただけでは十分に免疫を作ることはできないため、決められた回数の接種が必要となります。
B型肝炎・ヒブ感染症・小児の肺炎球菌感染症・百日せき・ポリオ・日本脳炎・インフルエンザ・HPV感染症・髄膜炎菌感染症・A型肝炎・狂犬病などの疾患を予防する目的で使われるワクチンです。
トキソイド
トキソイドとは、免疫を作る上で重要となる細菌の出す毒素の毒性をなくし、免疫を作る働きのみにした製剤です。
ほぼ不活化ワクチンと同じタイプの製剤といえますが、ジフテリアや破傷風などの予防接種に使われます。