脳波計の電極はどのような役割を持つのか?
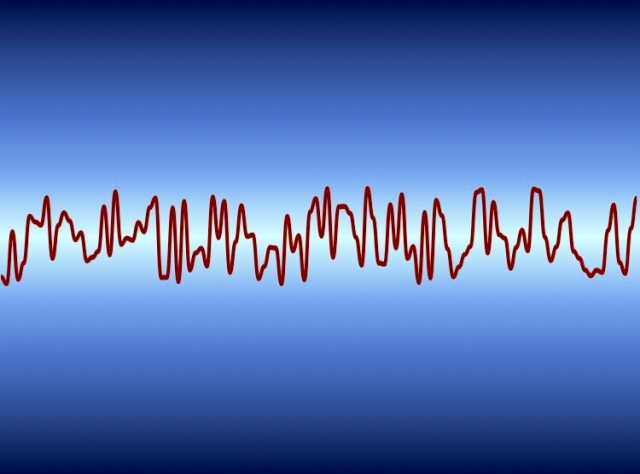
脳の活動状態を調べる際、脳波計では頭部に取り付ける電極を使用します。さて、この電極には一体どのような役割があるのでしょう。今回は、日本における脳波計の歴史について振り返りながら、脳波計の電極の役割についてご紹介します。
脳波計の歴史
日本においての脳波計は、1936年に東北大学で実験用として製作されたタイプが最初となります。その後、北海道大学・東京大学でも研究が始まり製作されました。
1943年、現在の文部科学省(旧文部省)の脳波研究班が組織され脳波計規格制定への取り組みが開始されます。名古屋大学・東北大学の研究者により討議された内容を反映し、1950年の『脳波班インク記録装置に関連した協議会』で規格が定められました。それを基に、東京大学生産技術研究員の手により臨床用の脳波計が試作されました。
1951年には東京大学工学部研究室の指導を受けた電機会社が木製号を商品化しました。それ以降の日本における脳波計の歴史は、次の通りです。
第1世代(真空管時代)は、先述した1951年の三星電機製木製号をその出発点とします。昭
和30年代には主に真空管が使用されていました。
昭和40年代には第2世代(トランジスタ・マイコン脳波計)の段階に入ります。この時期に開発されたタイプがオールトランジスタ式の脳波計です。トランジスタが使用されたことで小型化が進むこととなります。この時期の脳波計の耐用年数は、チャンネル数に合わせて要する電極、フィルタ、感度などを定めるロータリースイッチの寿命に左右されていました。
しかし、1975年前半に半導体スイッチが出て状況が変わります。またこのときマイクロコンピューターが採用され脳波計にブラウン管を使用した表示装置が登場しました。
その頃から、日本の脳波計はその性能と低価格から世界中で使用され始めました。世界市場の50%以上、アメリカでは70%以上の市場シェアを持つまでに至ります。
1990年代に入ると、脳波を電子的にファイリングする機能が備えられるようになります。それのタイプが第3世代(電子ファイリング)です。病院内における記録紙保管の問題、病院内のデータネットワーク整備の必要、加えてコンピューターを使用した判読の必要性などと言ったニーズに応える形で開発されたと言えるでしょう。
1993年以降、デジタル脳波計が販売され始めました。従来の脳波計(ファインリング)は紙記録同様のデータを、電子媒体に保存する形式が取られていました。しかしこの時期から、再構成ができる参考誘導(リファレンス)という方法で記録されるようになり、検査後に検出データを任意に組み合わせて脳波を作り出せるモンタージュが可能となりました。
現代では、脳の状態を間断なく評価する方法として脳波以外にも脳磁図や光トポグラフの原理が利用されるようになってきました。それらを用いる次世代の脳検査機器と比べると、脳波計は比較的低コストかつ操作が容易であることから、今後も脳関連の検査機器の主流であり続けることでしょう。
電極の役割
前項のような変遷を辿ってきた脳波計において、重要なパーツとも言える電極について見ていきたいと思います。
脳波を測るとき、被験者の頭皮に取り付けられるものが電極です。これにより、頭皮や頭蓋骨などを経て漏れてくる脳の活動電位が測定されます。1つの電極の検出対象範囲には数百万個以上の神経細胞があります。その無数の神経細胞から発せられる活動電位の総和を、装着された各電極によって検知するというわけです。
電極の配置は通常、国際脳波学会が推奨する「10/20法」に準じます。
この方式に則って、総数21個の電極が被験者頭部の特定箇所に装着されることになります。電極のうち両耳朶に位置する2個はアースとして用いられ、残り19個の電極装着箇所から脳波を象る電位差データが検知されることになるわけです。
まとめ
脳は活動の際に電気を発生します。その電気を活動電位として検知する電極の役割と脳波計の歴史について述べました。これから先の脳医療においても脳波計の更なる進化が期待されます。













