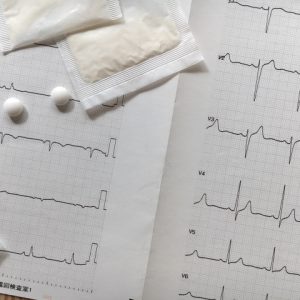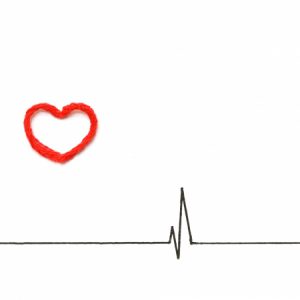腫瘍内科とは?専門疾患や検査の種類・内容について解説

医師が診察する身体の部位や疾病は、診療科ごとに大きく異なります。
診療科は複数あるものの、それぞれどのようなときに受診すればよいのか迷うこともあるでしょう。
そこで、腫瘍内科とはどのような診療科なのか、専門疾患や検査の種類・内容について解説していきます。
腫瘍内科とは
腫瘍内科とは、主にがんの薬物療法を担当する診療科です。
胃や大腸など消化器にできたがんや、原発不明がんなどの治療を担当することが多いといえます。
がん患者の診療すべてを包括する領域であるため、がんの早期診断・治療や、がん予防なども含みます。
従来のように臓器ごとに診療するのではなく、臓器横断的ながんに対する薬物療法を実施する診療科であるといえるでしょう。
腫瘍内科の専門疾患
腫瘍内科の専門疾患は、基本的には原発不明がんです。
どこから発生したがんなのか、検査をしてても判断がつかない悪性腫瘍に対し、抗がん薬治療を行います。
白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫など造血器腫瘍に対する診療と、貧血・出血傾向・血栓性疾患・不明熱などの疾患診療を専門とします。
腫瘍内科の検査
腫瘍内科では、臓器横断的にすべてのがんに対し、抗がん剤・ホルモン・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬による治療などを行います。
最新のデータに基づいた治療を行うためにも、主に次の検査を行った上で進めていくようです。
・CT検査
・エコー検査
・MRI検査
・腫瘍マーカー検査
それぞれの検査について説明します。
CT検査
「CT検査」とはX線を体の周囲へあてていき、体内の吸収率の違いをコンピュータで処理し、体の断面を画像にすることによる検査です。
がんの有無や、広がり、転移の有無などを確認したり調べたり、治療の効果の判定や再発の有無の確認など、色々な目的で実施されます。
エコー検査
「エコー検査」は、体の表面に超音波プローブをあてて、体内の臓器からはね返る超音波を画像に映し出すことによる検査です。
がんの位置や形、大きさ、周辺臓器との関係など確認するために行います。
MRI検査
「MRI検査」は、強力な磁場が発生しているトンネル状になった装置の中で、周波数の電波を体にあてて内部断面をいろいろな方向から画像として映し出す検査です。
がんの有無・広がり・他臓器への転移などの確認や、治療の効果を判定などで用いられます。
腫瘍マーカー検査
「腫瘍マーカー検査」とは、血液や尿など体液の成分から数値を測定することによる検査です。
分析装置により、腫瘍が存在した場合に急激に高まるマーカー値などを確認・測定します。
診断補助や診断後の経過・治療効果などを確認する目的で行われます。