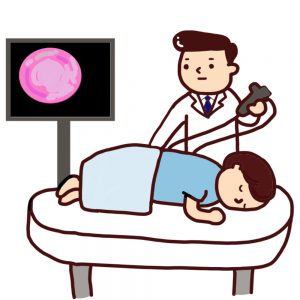聴診器とは?伝導音を聴く医療機器の構造や使い方を簡単に紹介

聴診器とは、たとえば患者の皮膚に当てることで、内部の振動により体内の音を聴く医療機器です。
医療現場では、呼吸音や心音を聴いて病気の診断や状態を確認します。
人が息を吐き出すとき、肺から気管支・気管・口・鼻へと空気が流れ、体の外に出ます。
この空気の流れを聴くことができるのが聴診器であり、それによって病気の診断につながります。
そこで、医師のトレードマークともいえる聴診器について、伝導音を聴く医療機器の構造や使い方を簡単に紹介します。
聴診器とは
聴診器とは、体内から発生する音を聴くための医療機器です。
医療における道具の1つであり、物体の表面に接触させて、内部から発生する可聴域の振動をチューブで導いて聴きます。
臨床医療の現場では、医師や看護師が患者の心臓・肺・血管の発生させる音を聴くために使います。
医療現場でステートと呼ばれることも多い医療機器であり、診療科別の使用割合では小児科が最も多く、次いで循環器科・内科・呼吸器科と続きます。
聴診器の構造
聴診器の構造は、チェストピース・チューブ(導管)・耳管部の3つで構成されます。
太く硬いチューブのほうが、雑音を入れずに正しい呼吸音を聴くことができます。
チェストピースの形状は、ベル型(ベル面)・膜型(ダイヤフラム面)の2つの種類があります。
ベル型の面で低音を聴き、膜型の面で高音を聴取できるなど、面によって聴取できる音が変わるため、聴取したい音に合わせた聴診器の面を選ぶことが必要です。
聴診器の使い方
聴診器は、機種によっては使い方が異なります。
液晶表示があるものや、リアルタイムで聴診音のデータ通信を可能とするタイプも存在します。
パソコン上で聴診音を、録音・保存・再生なども可能です。
先に説明したとおり、聴診器にはベル型と膜型の面があり、聴診したい音に合わせた面の使い分けが必要といえます。
たとえば呼吸音の聴診の場合は、膜型を使用します。
呼吸音には、正常音と異常音(ラ音)があります。
高齢で痩せている患者の場合、チェストピースが大きすぎると胸壁にフィットしないことも少なくないため、小児用の小さめの聴診器を使うとよいといえます。
心音を聴診するときには、膜型とベル型のどちらも使用するため、適切な使い分けが必要です。
膜型でⅠ音とII音を聴き、ベル型で低調性雑音の過剰心音(III音・IV音)を聴取することになります。