電子内視鏡とは?胃カメラとの違いや内視鏡検査の種類を簡単に紹介
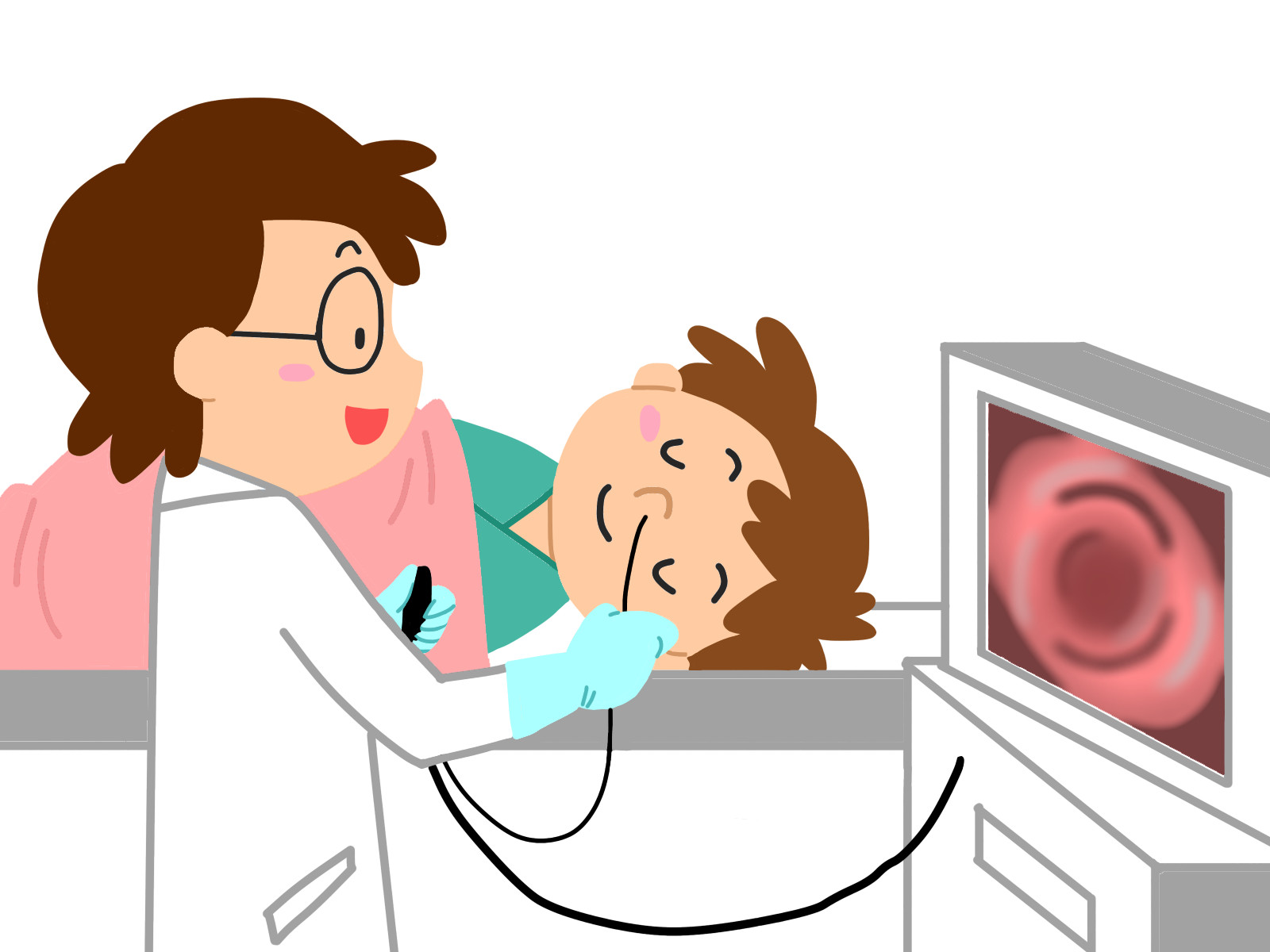
電子内視鏡とは、カメラ搭載の内視鏡(スコープ)を、口・鼻・肛門から挿入し、のど・食道・胃・十二指腸・大腸・膣などの臓器内部を直接観察できる医療機器です。
赤を除いた青と緑の光で観察する内視鏡であり、血液中のヘモグロビンが青色光を吸収して、粘膜表面の毛細血管を浮かび上がらせてがんなどの微細病変部を見やすくします。
そこで、電子内視鏡について、胃カメラとの違いや内視鏡検査の種類を簡単に紹介します。
電子内視鏡とは
電子内視鏡とはビデオ鼻咽腔スコープとも呼ばれる医療器具であり、鼻やのどを診るときに使用する軟性内視鏡です。
光ファイバーの開発によって生まれ、1970年代後半頃に従来までの胃カメラに代わり普及しました。
内視鏡と胃カメラは狭義では別物として扱われているものの、胃の検査に使う内視鏡は胃カメラと呼ばれることもあります。
内視鏡の特徴
従来までのファイバーと比べて解像度が高く、光を伝送する光ファイバーを使っています。
先端部にCCDと呼ばれる超小型カメラ(半導体素子)を備えており、胃の内部をリアルタイムで観察し、記録できます。
また、CCD以外にも照明・送気・送水管、生検鉗子孔が装備されており、高画質な映像でハイビジョン再生されます。
胃カメラとは
胃カメラとは、1950年に日本で開発された医療機器です。
挿入管の先端に、小型のスチルカメラと照明用の豆ランプが備わっています。
現在使用されている内視鏡のようにリアルタイムでモニタリングできなかったため、胃に先端が達したときに写真撮影し、検査終了後に現像して診断していました。
管も太かったため、検査にかかる時間も長めだったものの、開発当時は画期的なシステムとされていました。
内視鏡検査の種類
内視鏡検査と呼ばれる医療機器には、主に以下の種類があります。
・上部消化器内視鏡検査
・大腸内視鏡検査
それぞれ説明します。
上部消化器内視鏡検査
上部消化器内視鏡検査と胃内視鏡検査はほぼ同じ検査のことです。
食道・胃・十二指腸などの総称が上部消化管といえますが、経鼻内視鏡のメリットは経口内視鏡と比較するとスコープが舌の付け根に触れないために嘔吐反応を抑えられることといえます。
鼻道が狭いと挿入しにくいこともあるため、この場合は経口内視鏡を選ぶことが必要です。
大腸内視鏡検査
大腸内視鏡検査は、内視鏡を肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体や小腸一部の内部の検査です。
同時に生検用組織を採取することもでき、ポリープがあればその場で切除もできます。












