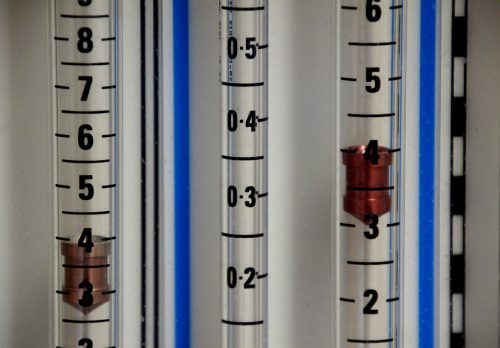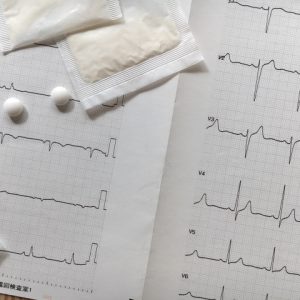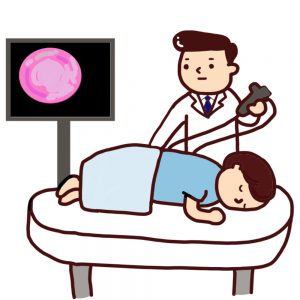脳波計の仕組みと検査で分かることについて
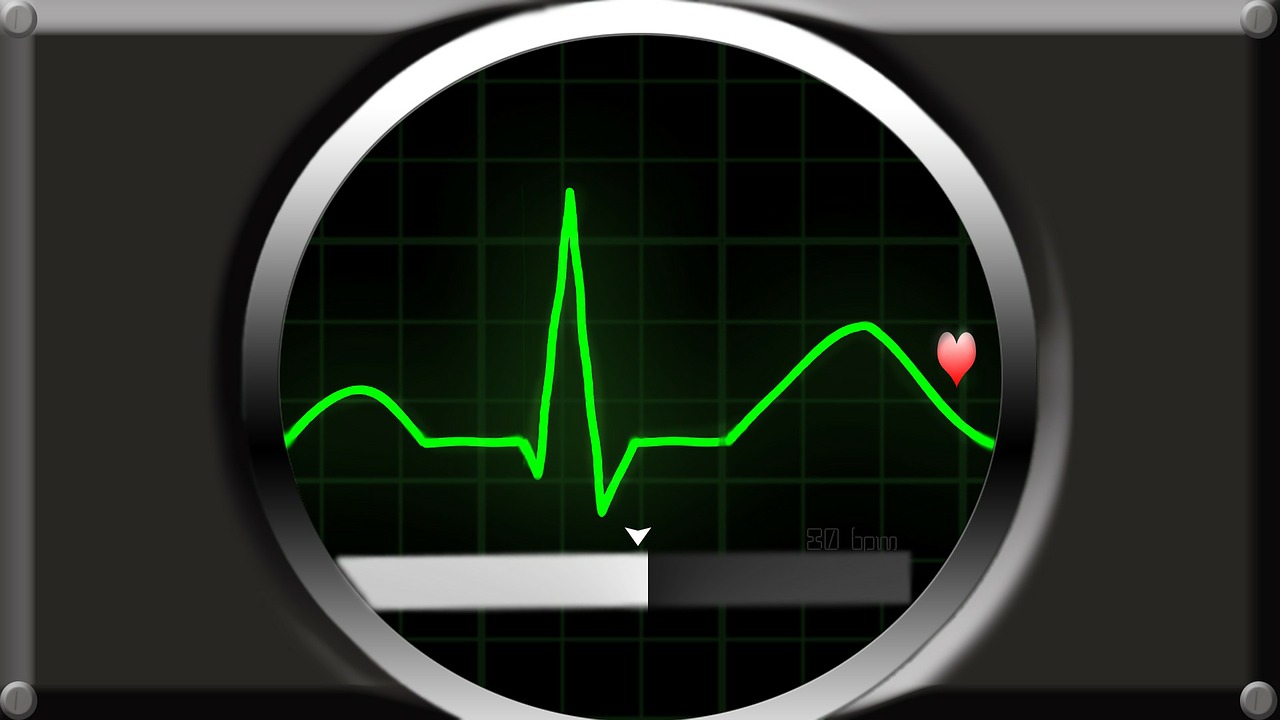
【はじめに】
脳波とは、簡単に言うと脳の中の電位変動や電気信号を捉えたもののことを言いますが、脳波計の仕組みを知ると、より脳波について知ることができます。
今回そんな脳波計の仕組みについて紹介してまいります。
【脳波計の仕組みとは】
脳波計とは脳の中の電気信号をとらえて測定する装置のことを言います。
また、脳内には140億個ほどのニューロンと呼ばれる神経細胞があり、この神経細胞を介して情報が電気信号として伝わります。私たちが日常動いたり考えたりできるのはこの電気信号の伝達がうまくいくことによってできるものと考えられています。
神経細胞の情報伝達は神経細胞間で化学物質を交換することによって行われます。
その際化学物質の放出に伴って微弱な電気信号が流れます。
この電気信号を増幅して記録することによって脳の動きや働きを観察することができ、その記録する装置のことを「脳波計」ということができます。
【脳波の測定で分かることとは】
脳波には4種類あるとされていてそれぞれデルタ波、シータ波、アルファ波、ベータ波という名前がついています。
またこれらの脳波の特徴としては「熟睡しているときなどに放出される」デルタ波、「目を閉じているときなどに放出される」アルファ波、「安静な状態で目を開いているときに放出される」ベータ波などということができます。
もし覚醒時にデルタ波やシータ波の放出が見られた際には、脳機能が低下している可能性があり脳挫傷、てんかん、脳の腫瘍がある疑いがでてきます。
その他にも意識障害や脳死の判定などにも脳波の測定は活用されます。
ただし、脳梗塞や脳出血などはCT装置やMRIなどで分かることもあり、脳波計での検査が脳の全ての異常を知る手段ではありません。
最近では、携帯型や自宅で測定できる脳波計もありますが、脳波の測定の際には電気を遮断したシールドルームで行われることが多く、頭部に電極を装着して安静に開いた状態で検査していきます。
【まとめ】
脳にはまだまだ謎が多く、脳波計で測定し分かる内容もまだまだごく一部であると言えます。
しかし脳波を測定することによって身体的な異常から精神病、「人の意識とは何か」といった抽象的な内容についての研究や解明までできるようになるかもしれません。
活動の指令を出す脳の働きを知るために脳波について知識を深め、役立てていただきたいと思います。是非参考にしてください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。